

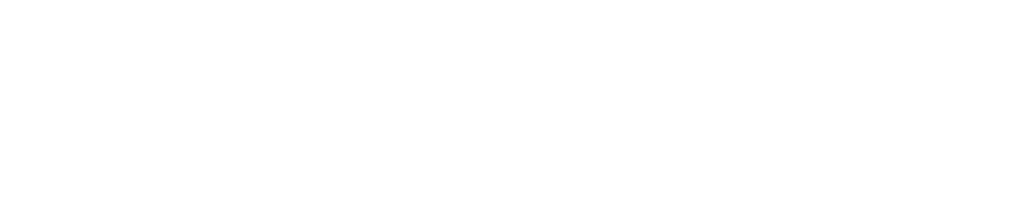
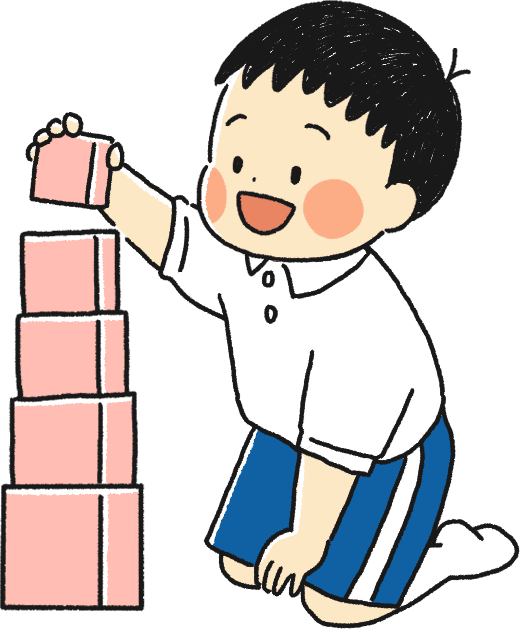
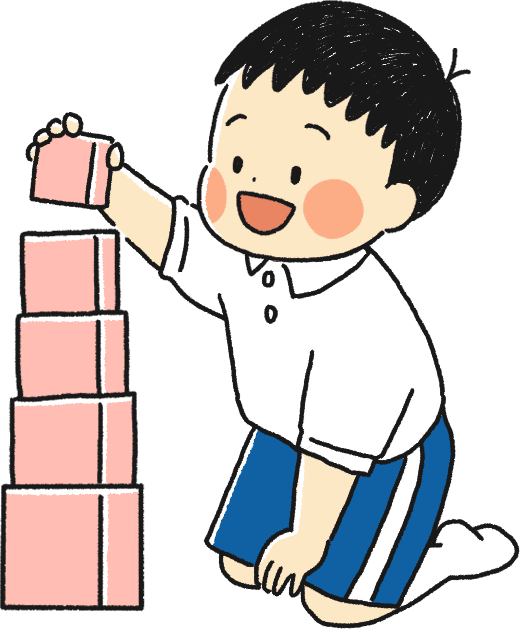 えんぜる保育園の保育
えんぜる保育園の保育
乳幼児期は、人生の土台を作る大切な時期です。生きる力の基礎をバランスよく育むため、計画に基づいて保育を行っています。
またモンテッソーリ教育を保育の土台とし、子ども自身の伸びようとする力を信じ「生活」「お仕事活動」「あそび」を通して「自立心」「主体性」を育んでいます。

 小規模保育(0・1・2歳児対象)
小規模保育(0・1・2歳児対象)
福岡市の小規模保育事業の一つで、えんぜる保育園を母体とした施設です。家庭的で、ゆったりとした雰囲気を大切にしながら、本園と同じ保育内容、給食、行事を行っています。
入園できるのは、保育が必要な0・1・2歳児の子どもです。

 採用情報
採用情報
えんぜる保育園では、幅広い年代の先生方が子どもたちと共に成長し、明るく元気に、保育を行っています。笑顔いっぱいのえんぜる保育園で、一緒に働きませんか?